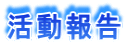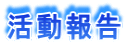「岡山の自然を学ぶ会」は,
自然観察の魅力を子供たちに体験的に学ばせたいと願った教育関係者や自然観察・環境教育に関心のある有志で構成されています。
自然のふしぎと感動を味わい 生き物の精妙さに気づいて 将来にわたって自然の事物・現象と対話し続けたいと考え 毎月そのときの季節の旬を感じる観察会を身近なフィールドで行っています。
顧問
岡山大学名誉教授 上島 孝久
岡山大学名誉教授 草地 功
岡山大学特任教授 荒尾 真一
元山陽新聞記者 内山 峰人
会 長 吉岡 勉
副会長 森本 章男
事務局 野稲 幸男 安廣 孝明, 藤本 義博

子ども達と
「旬を感じる」
自然との対話を求めて
藤本 義博(岡山県「教育時報」平成18年2月号) |
季節は「如月」。名前の由来には諸説あるようだが、旧暦二月でもまだ寒さが残っているので、衣(きぬ)を更に着る月であるから「衣更着(きさらぎ)」ともいう。この冬は、大雪をもたらした前年よりさらに厳しく、冷気は北風に吹き飛ばされた氷の剣だ。こんな折、風が少々収まれば、衣を更に着込んで、ネイチャースキーやスノーシューを備え、子ども達と雪原に出かける。盛冬の旬を感じる会の一コマだ。ノウサギやホンドキツネの足跡との出会いを求めて。
季節は「卯月」。卯の花(ウツギの花)が咲く季節なので、「卯の花月」の略とする説が有力とされ、一年の循環の最初を意味する。日のぬくもりがしみ渡る日向は、乳飲み子を包み込んだ乳房の柔らかさだ。こんな折、剪定ばさみを備え、子ども達と里山に出かける。初春の旬を感じる会の一コマだ。コシアブラやタカノツメ、ハリギリの若芽との出会いを求めて。
季節は「水無月」。水無月の「無」は、「の」にあたる連体助詞「な」で、田に水を引く月であることから「水の月」を意味する。空気をしぼれば、天のしずくがほとばしる瑞々しさだ。こんな折、懐中電灯を備え、子ども達と夜の小川や雑木林に出かける。初夏の旬を感じる会の一コマだ。デート中のアマガエルやゲンジボタル、樹液のレストランに集まるクワガタムシとの出会いを求めて。
季節は「神無月」。神を祭る月であることから、「神の月」とも、新穀で酒を醸す月なので、「醸成月(かみなしづき)」が転じ、「神無月」になったともいう。実りの恵みを運ぶ透き通った風は、切り子のグラスだ。こんな折、竹かごを腰に備え、子ども達とブナの森に出かける。晩秋の旬を感じる会の一コマだ。クリタケやナメコ、ブナやトチの実との出会いを求めて。
子ども達と体験する様々な「旬を感じる会」は、「岡山の自然を学ぶ会」の活動の一つである。「岡山の自然を学ぶ会」は、自然観察の魅力を子供たちに体験的に学ばせたいと願った教育関係者や自然観察・環境教育に関心のある有志で2年前に結成された会である。月に一度程度、前述の「旬を感じる会」の他、ある大学の研究室に集まり楽しみながら生物教材を考える「やちゃぼうの会」、身近な植物をデジカメに記録しながら学ぶ「草花探検隊」の3本柱から成る。自然のふしぎと感動を味わい、生き物の精妙さに気づいて、将来にわたって自然の事物・現象と対話し続ける子ども達を育てたいと考え、毎月そのときの季節の旬を体験する活動を身近なフィールドで行っている。
自然の前では、大人と子ども、教える者と教わる者の境界はない。人として等しく自然から共に感じ学び、感謝、感動を分かち合うのである。人としての日々の暮らしが、生きものと生きものを育む自然環境に支えられていることを実感しながら。
多くの子ども達と共に、将来にわたって自然と対話し続けていきたいと願いながら、多忙な仕事の合間に遊びの計画を練るのが私らしさの一コマでもある。
|
|